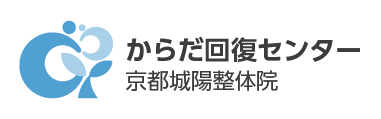
 院長:柴田
院長:柴田お気軽にご相談ください!
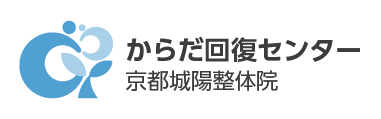
 院長:柴田
院長:柴田お気軽にご相談ください!


こんにちは、からだ回復センター京都城陽整体院の柴田です。最近、「なんだか調子が悪いな」と感じることが増えていませんか?頭がぼーっとする、夜なかなか眠れない、疲れが取れない…そんな不調の背景には、自律神経失調症が関わっているかもしれません。
実は、神経の働きを整えるには、日々の食事から摂る栄養がとても大きな役割を果たしています。
私は管理栄養士としての経験と治療家としての臨床経験を重ねる中で、体の内側から整えることの大切さを実感してきました。今日は、そんな神経を支える栄養の話を、皆さんにお伝えしたいと思います。


栄養と整体、両方の視点から皆さんの健康をサポートしています
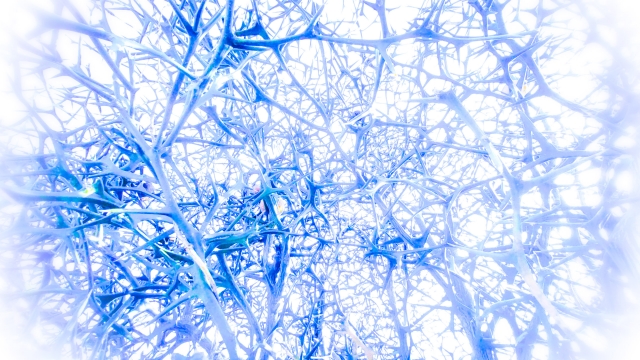
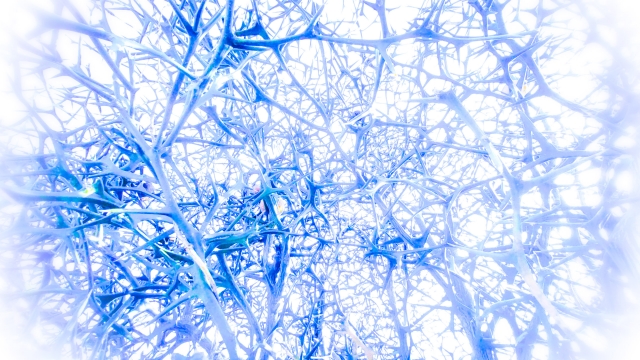
私たちの体は、食べたものから作られています。これは単なる比喩ではなく、科学的な事実です。神経伝達物質と呼ばれる、脳や神経が情報をやり取りするための大切な物質も、食事から摂った栄養素をもとに体の中で作られているのです。
たとえば、気持ちを安定させるセロトニンという物質があります。このセロトニンは、トリプトファンというアミノ酸から作られます。
また、やる気や集中力に関わるドーパミンやノルアドレナリンは、チロシンというアミノ酸が材料になっています。つまり、必要な材料が不足していれば、神経が正常に働くことができなくなってしまうのです。
さらに、神経細胞そのものを守り、修復するためにも、ビタミンやミネラルといった栄養素が欠かせません。現代の食生活では、カロリーは足りていても、こうした微量栄養素が不足しがちになっているケースが多く見られます。
ここからは、具体的にどんな栄養素が神経の働きを支えているのか、一つひとつ見ていきましょう。難しい話に聞こえるかもしれませんが、身近な食材に含まれているものばかりですので、安心してくださいね。


トリプトファンは、先ほどお伝えしたセロトニンの材料となる必須アミノ酸です。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、心を落ち着かせたり、睡眠の質を高めたりする働きがあります。トリプトファンは体内で合成できないため、食事から摂る必要があります。
大豆製品、バナナ、ナッツ類、乳製品、卵などに多く含まれています。
朝食に納豆とバナナ、ヨーグルトを組み合わせるだけでも、しっかりとトリプトファンを摂ることができます。また、トリプトファンがセロトニンに変わるためには、ビタミンB6やマグネシウムも必要ですから、単独ではなくバランスよく摂ることが大切です。


ビタミンB群は、神経の働きを支える上で欠かせない栄養素です。特にビタミンB1、B6、B12は、神経伝達物質の合成やエネルギー代謝に深く関わっています。不足すると、疲労感やイライラ、集中力の低下といった症状が現れやすくなります。
ビタミンB1は豚肉や玄米、全粒粉のパンに多く含まれます。ビタミンB6はレバーや鶏肉、魚類に豊富です。ビタミンB12は動物性食品に多いため、菜食中心の方は特に意識して摂る必要があります。
私の家では、発酵発芽玄米を主食にして、おかずも多品目を心がけています。加工食品をほとんど使わないのも、こうしたビタミンをしっかり摂るためです。


マグネシウムは、神経の興奮を抑え、筋肉の緊張を和らげる働きがあります。ストレスがかかると体内のマグネシウムは消費されやすくなるため、現代人は慢性的に不足しがちだと言われています。不足すると、神経が過敏になり、ちょっとしたことでイライラしたり、不安を感じやすくなったりします。
海藻類、ナッツ類、大豆製品、魚介類に多く含まれています。特に、ひじきやわかめ、アーモンドなどは手軽に取り入れられる食材です。また、入浴剤としてエプソムソルト(硫酸マグネシウム)を使うことで、皮膚からもマグネシウムを吸収できると言われています。


オメガ3脂肪酸は、脳や神経細胞の膜を構成する重要な成分です。特にDHAやEPAといった成分は、神経伝達をスムーズにし、炎症を抑える働きがあります。現代の食生活では、オメガ6脂肪酸(サラダ油など)の摂取が多く、オメガ3脂肪酸が不足しがちです。
青魚(サバ、イワシ、サンマなど)、亜麻仁油、えごま油、くるみなどに豊富に含まれています。
週に2〜3回は青魚を食べるようにすると良いでしょう。油を選ぶ際にも、揚げ物に使う油は控えめにして、亜麻仁油やえごま油をドレッシングとして活用するのがおすすめです。
GABAは、神経の興奮を抑える抑制性の神経伝達物質です。ストレスを和らげ、リラックスした状態を作り出す働きがあります。近年、GABAを含む機能性食品も注目されていますが、食事からも摂取することができます。
発芽玄米、トマト、じゃがいも、キムチや味噌などの発酵食品に含まれています。特に発芽玄米は、通常の白米に比べて数倍のGABAが含まれており、私自身も毎日の食卓に取り入れています。発酵食品は腸内環境も整えてくれるため、一石二鳥ですね。
神経を整えるために摂りたい栄養素がある一方で、控えた方が良い食習慣もあります。これは完全に避けるというよりも、摂りすぎに注意するという意識が大切です。
まず、カフェインの摂りすぎには注意が必要です。
コーヒーや紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインは、一時的に気分をシャキッとさせてくれますが、過剰に摂ると神経を過度に刺激し、不安感や不眠を引き起こすことがあります。特に夕方以降は控えるようにしましょう。
次に、精製された糖質の摂りすぎです。
白砂糖や白米、菓子パンなどは血糖値を急激に上昇させ、その後急降下させます。この血糖値の乱高下は、神経の興奮や疲労感、イライラを引き起こします。甘いものが欲しくなったときは、果物やナッツ、少量のダークチョコレートを選ぶと良いでしょう。
また、アルコールの過剰摂取も神経系に負担をかけます。適量であればリラックス効果がありますが、飲みすぎると睡眠の質を下げ、翌日の体調不良につながります。休肝日を設けることも大切です。
加工食品やインスタント食品には、保存料や人工的な添加物が多く含まれています。これらは体にとって異物であり、解毒のために肝臓や腎臓に負担をかけます。できるだけ素材そのものの味を活かした、シンプルな調理を心がけることをおすすめします。


何を食べるかと同じくらい、いつ、どのように食べるかも大切です。不規則な食事は血糖値の乱れを招き、神経系にストレスをかけてしまいます。
朝食は一日のスタートとして、しっかり摂ることが理想です。タンパク質と複合糖質を組み合わせることで、血糖値が安定し、午前中のパフォーマンスが向上します。たとえば、発芽玄米のおにぎりと納豆、味噌汁と野菜のおひたしといった和食の組み合わせは、神経を整える栄養素がバランスよく摂れます。
昼食では、エネルギー源となる炭水化物と、疲労回復に必要なビタミンB群を意識しましょう。丼ものや麺類だけで済ませるのではなく、野菜や魚、肉などを組み合わせた定食スタイルが理想的です。
夕食は、寝る3時間前までに済ませることが大切です。遅い時間に食べると、消化にエネルギーが使われ、睡眠の質が低下します。また、夕食には副交感神経を優位にするために、温かい汁物やリラックス効果のある食材を取り入れると良いでしょう。


ここまで栄養の話を中心にお伝えしてきましたが、私が治療家としても活動しているのには理由があります。それは、どんなに良い栄養を摂っても、体のバランスが崩れていれば、栄養が十分に行き渡らないからです。
姿勢の歪みや筋肉の緊張は、血流を妨げ、栄養や酸素が細胞に届きにくくなります。また、背骨の歪みは自律神経の働きにも影響を及ぼします。当院では、姿勢分析や各種検査を通じて、あなたの体がどのような状態にあるのかを丁寧に見極めます。
そして、脊柱軸整法という独自の整体技術で、体のバランスを整えていきます。同時に、管理栄養士としての知識を活かして、あなたに合った食事のアドバイスもさせていただきます。
体の外側と内側、両方から整えることで、より早く、より確実に健康を取り戻すことができるのです。


神経を整えるための食事と聞くと、「難しそう」「続けられるかな」と不安に思うかもしれません。でも、完璧を目指す必要はありません。まずは、今日からできる小さな一歩を踏み出してみてください。
たとえば、朝食にバナナを一本追加する、コーヒーを一杯減らしてハーブティーにしてみる、夕食に青魚を取り入れてみる。そんな小さな変化の積み重ねが、やがて大きな違いを生み出します。
私自身、家族の食事を担当していますが、特別なことをしているわけではありません。発酵発芽玄米を炊いて、旬の野菜をたっぷり使って、魚や大豆製品を中心に、一汁三彩の食卓を心がけています。子どもたちも、そんな食事のおかげで元気に過ごしています。
あなたも、無理のない範囲で、楽しみながら食事を見直してみてください。そして、もし「自分ではどうしたらいいかわからない」「体の不調がなかなか改善しない」と感じたら、どうか一人で悩まず、私に相談してください。


一緒に、健康への一歩を踏み出しましょう
神経のバランスを整えることは、心と体の両方を健やかに保つための土台です。そして、その土台を作るのは、毎日の食事です。
食べることは、生きること。そして、よりよく生きるための大切な手段でもあります。
栄養と整体、両方の視点から皆さんの健康をサポートできることが、私の強みであり、喜びでもあります。あなたがまた笑顔で、やりたいことを存分に楽しめる毎日を取り戻せるよう、全力でサポートさせていただきます。
どんな小さなことでも構いません。気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。一緒に、健康への一歩を踏み出しましょう。

