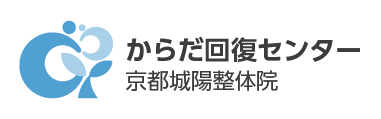
 院長:柴田
院長:柴田お気軽にご相談ください!
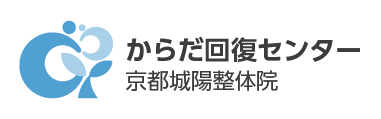
 院長:柴田
院長:柴田お気軽にご相談ください!




自律神経の不調について調べていると、「これをすれば良くなる」「原因はこれだ」そんな“答え”がたくさん見つかります。
でも、実際にお話を伺っていると、ひとつの正解だけで回復していく方は、ほとんどいません。
「なんとなく体がだるい」「朝がつらい」「気持ちが落ち込みやすい」そんな日が続くと、自分でもどうしていいのかわからなくなってしまいますよね。
病院で検査をしても「異常なし」。薬を飲んでも、良くなった気がしない。「このままずっと不調と付き合っていくしかないのかな……」そんなふうに思ってしまうこともあるかもしれません。
でも、ちょっと待ってください。
もしかすると、あなたのその不調は、体のバランスや回復力がうまく働いていないことが関係しているのかもしれません。
その背景のひとつとして、栄養や腸の状態が影響しているケースもあります。
私たちの体も心も、日々の食べ物から作られています。食べることは、単にお腹を満たすだけでなく、細胞や神経、ホルモンの働きまでも支える、まさに“土台”のような役割をしています。
だからこそ、その土台が少し崩れると、自律神経がうまく働かなくなり、心や体にさまざまな不調として現れてしまうことがあるのです。
これは決して、食べ方が悪いとか、自己管理ができていないとか、そういう話ではありません。現代の食環境や生活スタイルの中では、誰にでも起こり得る自然なことなのです。
だからこそ、責めないでくださいね。
このコラムでは、自律神経の不調と「栄養」のつながりについて、わかりやすく、そして少しやさしく掘り下げていきたいと思います。
読んでくださるあなたが、「なるほど、そういうことだったんだ」と少しでもホッとできたり、「ここから変えてみよう」と思えるきっかけになれば嬉しいです。


自律神経は、私たちが意識しなくても体の中を整えてくれている“すごい仕組み”です。呼吸や血流、消化、体温の調整、ホルモンの分泌など、命を守るための働きのほとんどを、この自律神経が静かにこなしてくれています。
ところが最近、この自律神経のバランスを崩す方がとても増えています。
ストレス、働きすぎ、不規則な生活…。そうした外側の要因ももちろん関係していますが、見落とされがちな“もうひとつの理由”があります。
それが、「体の中の材料=栄養素が足りていない」ことです。
たとえば「元気を出したいときに必要なホルモン」や「気持ちを落ち着ける神経伝達物質」は、脳の中で作られています。でも、それを作るためには、材料が必要なんです。
その材料になるのが――
たんぱく質(アミノ酸)、ビタミンB群、鉄、亜鉛、マグネシウム、そして脂質などの栄養素です。
どれかひとつでも不足すると、うまく作れなかったり、働きが鈍くなってしまいます。そうなると、気分が落ち込みやすくなったり、イライラしやすくなったり、体が緊張しっぱなしになったり…。自律神経が乱れた状態へとつながっていってしまうのです。
栄養不足と聞くと「ちゃんと食べているから大丈夫」と思われる方も多いのですが、実は問題はもっと“深いところ”にあります。
現代の生活では、こうしたことが重なり合って、気づかないうちに“足りていない体”になっている方がとても多いのです。
自律神経の乱れや心の不調は、本人が「弱いから」とか「我慢が足りないから」と思いがちですが、それは違います。多くの場合、自律神経の乱れや心の不調は、性格や気の持ちようの問題ではありません。
ストレスや生活習慣などが重なる中で、脳や神経が働くために必要な栄養が、知らないうちに不足しているケースも少なくないのです。
自律神経そのものが壊れたわけではありません。働くための条件がそろわず、本来の調整力を発揮しにくい状態が続いていただけなのです。
だからこそ、栄養という視点から体を見直し、必要な条件が整ってくると、自律神経は本来持っている「整おうとする力」を、もう一度発揮しはじめます。それは、無理にがんばることではなく、これまでがんばってきた体を、正しく支え直すということなのです。
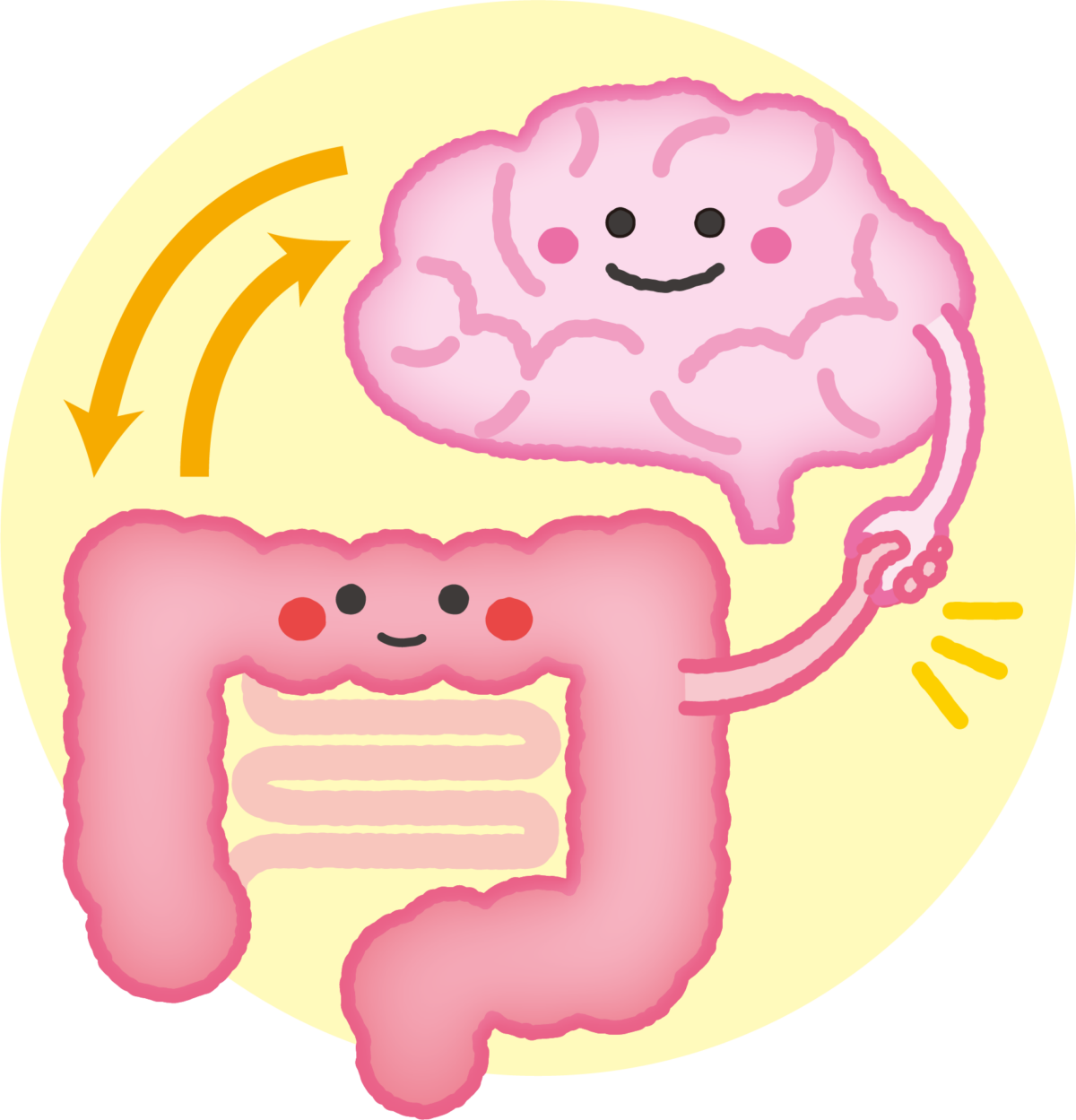
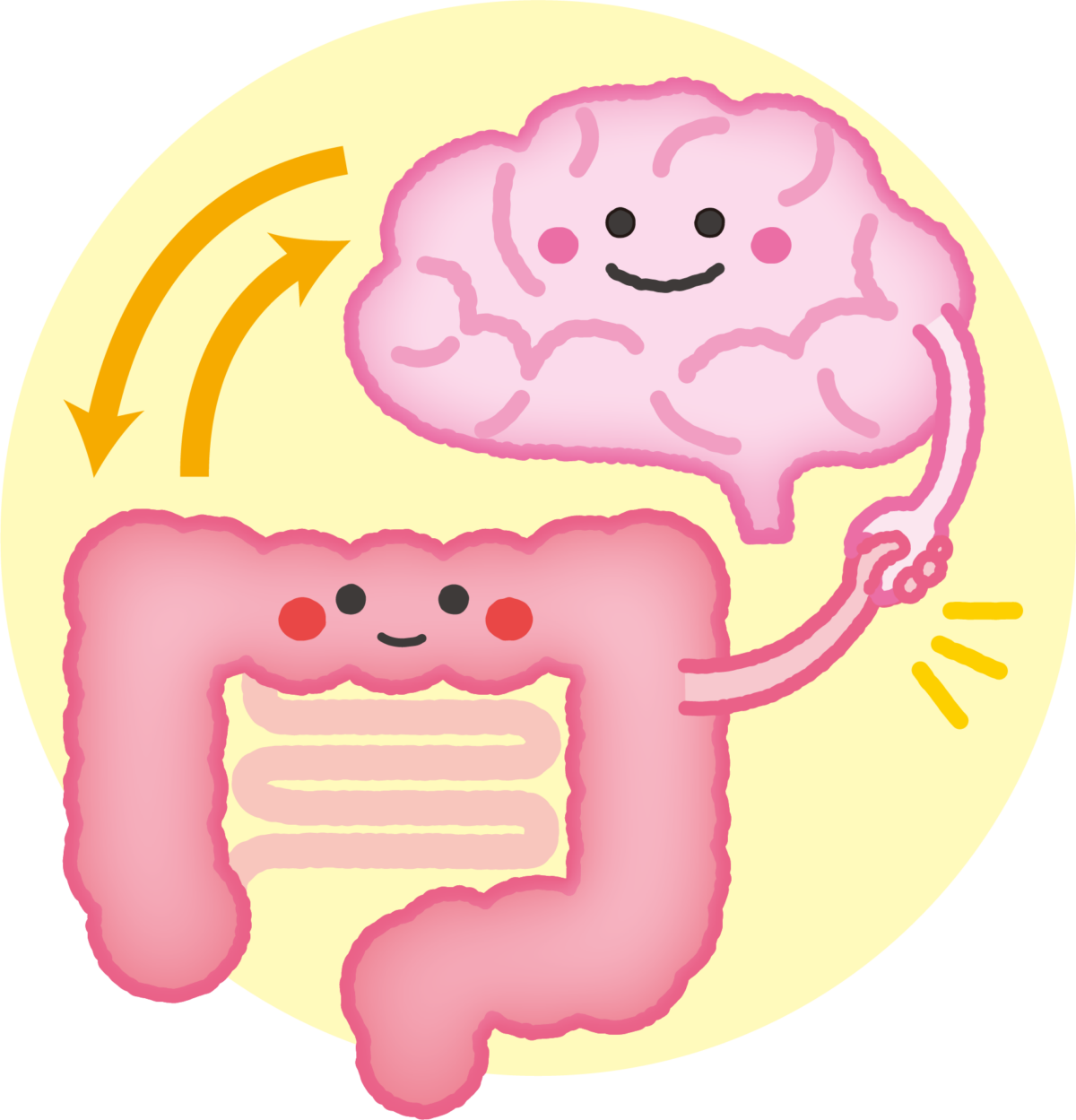
ストレスを感じると、お腹が痛くなったり、便がゆるくなったり…。そんな経験、ありませんか?
また逆に、腸の調子が良くない日には、なんだか気分まで沈んでしまったり、イライラしやすくなったりすることも。
実はこれ、「気のせい」ではないんです。
脳と腸は、まるで会話をしているかのように、日々情報をやりとりしています。これを医学的には「脳腸相関(のうちょうそうかん)」と呼びます。
脳から腸へはもちろん、腸からも脳へと信号が送られており、どちらかの調子が崩れると、もう一方にも影響が出る――そんな密接な関係なのです。
特に、腸には「腸管神経系(ちょうかんしんけいけい)」と呼ばれる独自の神経ネットワークが存在し、その神経の数はなんと脳に次いで多いと言われています。
だからこそ、腸の状態は心の状態にも、そして自律神経のバランスにも強く関係してくるのです。
セロトニンという言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。「幸せホルモン」とも呼ばれ、気分を安定させたり、ストレスを和らげたりする働きがあります。
実はこのセロトニン、体内にあるうちの約9割が腸の中で作られているのです。
つまり、腸の環境が整っていなければ、セロトニンがしっかり作られず、脳にも伝わりにくくなってしまうのです。
腸の不調が続くと、なぜか不安感やイライラ、やる気の低下を感じやすくなるのは、このためでもあります。
腸が元気になると、神経もホルモンもスムーズに働くようになります。逆に、便秘や下痢が続いていたり、ガスがたまりやすいなどの状態があると、自律神経のバランスも乱れがちになります。
日々の小さな「おなかのサイン」は、実は体全体のバランスを映す“鏡”のようなもの。
もし思い当たることがあるなら、腸にやさしい生活を心がけることで、心や体が少しずつ整っていくかもしれません。
自律神経を整える第一歩として、「腸を整えること」はとても大切な視点です。
では、腸を整えるために、日常生活でどんなことから始めれば良いのでしょうか。
前の章でお伝えしたように、腸はただの消化器官ではありません。心の状態にも、自律神経のバランスにも影響を与える、大切な“もう一つの脳”のような存在です。
そんな腸を、少しでも元気にしていくことができたら――
それは、今のあなたの不調をやわらげる大きな一歩になるかもしれません。
※ここでは、一般的に腸をいたわるための考え方をご紹介します。すべてを行う必要はありません。
腸を整えることは、決して特別なことではありません。むしろ、ちょっとした日々の積み重ねが、腸を少しずつ元気にしてくれます。


たとえば、こんなことから始めてみるのもいいかもしれません。
どれも当たり前のようなことかもしれませんが、腸はとても繊細で、こうした日々の“やさしさ”を確かに受け取ってくれます。
「毎日〇〇をしなければいけない」「完璧な食事を目指さなきゃ」――そんなふうに構えてしまうと、かえって心も体も疲れてしまいます。
腸は、プレッシャーにも敏感です。
だからこそ、「できるときに、できることを」「気づいたときに、ちょっと変えてみる」くらいの軽やかな気持ちで大丈夫。
自分にとって心地よいこと、続けられそうなことを、ひとつだけ見つけてみてください。それが、腸内環境を整えるスタートラインになります。
腸の調子が良くなると、便通がスムーズになるだけでなく、呼吸が深くなったり、疲れにくくなったり、自然と気持ちも前向きになってくることがあります。
「朝が少し楽になった」「気づいたら、イライラすることが減っていた」そんな小さな変化が、気づけば“生きやすさ”につながっていくのです。
あなたの腸は、あなた自身が整えてあげることができます。そしてその変化は、きっと自律神経の働きにも、心の落ち着きにも、じわじわと届いていきます。


栄養や腸内環境は、自律神経の安定に関わる大切な土台です。自宅で少しずつ意識するだけでも、体の反応が変わることがあります。ただし、効果の出方には個人差があり、栄養だけで劇的に変化することは稀です。
より早く、確実に体のバランスを整えたい方は、姿勢や呼吸、筋肉の緊張をゆるめる整体的なアプローチと組み合わせることも有効です。
次の記事では、当院が自律神経を整えるために、体の内側(栄養・腸)と外側(姿勢・呼吸・体の緊張)をどのように考えているのかを、できるだけやさしく整理しています。
▶︎ 【体の内側と外側、両方から自律神経を整えるという考え方】
この記事では、自律神経失調症について、整体の視点からお伝えしてきました。
症状別のページでは病院との役割の違いや、当院での考え方、実際に来院された方の声なども紹介しています。「自分の状態に近いかもしれない」そう感じる部分があれば、参考にしてみてください。


――――――――――
からだ回復センター京都城陽整体院
からだ回復センター京都城陽整体院には、城陽市・宇治市・京田辺市を中心に、京都府南部にお住まいの方が多く来院されています。
病院で「異常はない」と言われたものの、体の不調が続いて不安を感じている方や、薬だけに頼らず、体の状態を整えていきたいと考えている方からご相談をいただくことが多い整体院です。
アクセス・通いやすさについて
※京都市内や奈良県からお越しの方もいらっしゃいます。対応エリア外にお住まいの方も、どうぞお気軽にご相談ください。