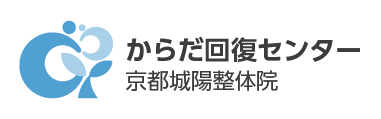
 院長:柴田
院長:柴田お気軽にご相談ください!
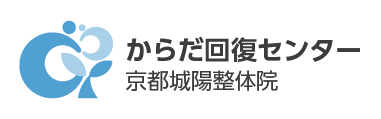
 院長:柴田
院長:柴田お気軽にご相談ください!


こんにちは。最近、雨が降る前になると頭が痛くなったり、台風が近づくと体が重くてだるくなったりしていませんか。実はそれ、天気痛と呼ばれる症状なのです。
天気によって体調が左右されるなんて不思議に思われるかもしれませんが、日本人の約6割が経験していると言われており、決して珍しいことではありません。
なぜ天候が変わると身体に不調が出るのでしょうか。その原因を正しく理解することで、症状の改善にもつながっていきます。このページでは、天気痛がなぜ起こるのか、そのメカニズムと本当の原因について、栄養と身体の両面を知っている私の視点から詳しくお伝えしていきます。


天気痛は誰にでも起こりうる症状です。決して気のせいではありませんので、ご安心ください


天気痛とは、気圧や気温、湿度といった気象条件の変化によって頭痛やめまい、関節痛、倦怠感などが引き起こされる症状のことを指します。医学的には「気象病」とも呼ばれ、雨が降る前や台風が接近する際に症状が強まるのが特徴です。
こうした症状は特に女性に多く、年齢を問わず幅広い世代で見られますが、病院で検査をしても異常が見つからないことがほとんどです。そのため「どこに相談すればいいのか分からない」と不安を抱えたまま過ごしている方が数多くいらっしゃいます。
天気痛によって現れる症状は人それぞれ異なりますが、次のような症状でお悩みの方が多くいらっしゃいます。


これらの症状は一つだけ出る場合もあれば、複数が同時に現れることもあります。天気が回復すると自然と軽快することが多いのですが、繰り返し症状が出ることで日常生活に支障をきたすようになるのです。
では、なぜ天気が変わるだけで身体に不調が起こるのでしょうか。そのメカニズムには主に「気圧の変化」と「自律神経の乱れ」が深く関わっています。


天気が崩れる際には気圧が低下します。この気圧の変化を私たちの身体は耳の奥にある内耳という器官で感じ取っています。内耳には気圧センサーのような働きがあり、急激な気圧変動を察知すると脳に信号を送り、身体にさまざまな反応を引き起こすのです。
特に内耳が敏感な方は、わずかな気圧変化でも強く反応してしまい、それが頭痛やめまいといった不調につながります。この内耳の感受性には個人差があり、遺伝的な体質や過去の耳の病気の影響も関係していると考えられています。
内耳が気圧の変化をキャッチすると、その情報は脳の視床下部という場所に伝わります。視床下部は自律神経の司令塔であり、交感神経と副交感神経のバランスを調整している大切な器官です。
気圧が急激に変化すると、自律神経のバランスが乱れてしまい、交感神経が過剰に働いたり、逆に副交感神経が強く出すぎたりします。このアンバランスこそが、天気痛のさまざまな症状を引き起こす直接的な原因となっているのです。
自律神経が乱れることで血管の収縮や拡張がうまく調整できなくなると、血流が不安定になり頭痛や肩こりが起こりやすくなります。また、筋肉の緊張が強まることで、関節や首、背中などの痛みも出やすくなります。
さらに、気圧が下がると体内の血管や組織が膨張しやすくなり、神経を圧迫して痛みを感じることもあります。このように、気圧の変化は身体の内側からじわじわと影響を及ぼすのです。
ここまで気圧と自律神経の話をしてきましたが、実は天気痛の根本的な原因はもっと深いところに隠れています。当院に来られる患者さまの多くは、気圧の変化そのものよりも、その変化に対応できない身体の状態に問題があるのです。


長時間のデスクワークやスマホの使用によって、現代人の多くが猫背や巻き肩といった姿勢の乱れを抱えています。姿勢が崩れると背骨や骨盤の歪みが生じ、自律神経が正常に働かなくなってしまうのです。
背骨の中には脊髄という大切な神経が通っており、背骨の歪みはその神経の働きを妨げます。結果として、気圧の変化に対する適応力が低下し、天気痛が起こりやすくなります。
日々の仕事や家事、人間関係などから受けるストレスも大きな要因です。ストレスが続くと交感神経が優位になったままになり、副交感神経が十分に働けず、自律神経のバランスが崩れたまま固定されてしまいます。
また、睡眠不足や食生活の乱れによる疲労の蓄積も、身体の回復力を低下させ、気象の変化に弱い状態をつくり出します。
自律神経の働きを支えるためには、ビタミンやミネラル、良質なタンパク質といった栄養素が欠かせません。しかし、忙しさから食事が疎かになったり、加工食品に偏った食生活を続けたりしていると、身体は栄養不足の状態に陥ります。
特にビタミンB群やマグネシウム、鉄分などが不足すると、神経の働きが鈍り、自律神経が安定しにくくなります。管理栄養士としての経験から申し上げると、天気痛でお悩みの方の多くに栄養面での課題が見受けられます。
女性の場合は、生理周期や更年期によるホルモンバランスの変動も大きく影響します。エストロゲンなどの女性ホルモンは自律神経と密接に関係しており、ホルモンが不安定になると自律神経も乱れやすくなります。
そのため、月経前や排卵期、更年期の時期には特に天気痛の症状が強く出る傾向があります。


天気痛の改善には、気圧の変化そのものをコントロールすることはできませんが、その変化に負けない身体をつくることが何より重要です。そのためには、まず今のあなたの身体がどのような状態にあるのかを正確に把握することが必要です。


当院では、天気痛の原因を一つに決めつけず、姿勢や自律神経の状態、呼吸の質、栄養状態、生活リズムなど多角的に検査を行います。姿勢分析ソフトを使った客観的な評価に加え、筋力検査やバイタルチェック、栄養調査などを丁寧に実施し、あなたの身体に何が起こっているのかを明らかにしていきます。
原因がはっきりしないまま対症療法を続けていても、症状は繰り返すばかりです。だからこそ、検査によって根本原因を見つけることが改善への第一歩になるのです。
当院の施術では、背骨の生理的弯曲や体幹の軸を整えることで、自律神経が正常に働ける環境をつくります。脊柱軸整法という当院独自の技術は、姿勢を整え、神経の流れを改善し、血流を促進することで、身体が本来持っている自然治癒力を最大限に引き出します。
痛みを伴わない優しい施術ですので、小さなお子さまからご高齢の方まで安心してお受けいただけます。
施術だけでなく、日常生活での過ごし方も大切です。十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動、ストレスのコントロールなど、生活全体を見直すことで天気痛に負けない身体が育っていきます。
管理栄養士としての知識を活かし、あなたに合った食事や栄養のアドバイスもさせていただきますので、身体の内側からも整えていくことが可能です。
天気痛は気圧の変化によって引き起こされる症状ですが、その背景には姿勢の乱れ、自律神経の不調、栄養不足、ストレスなど、複数の原因が絡み合っています。大切なのは、表面的な症状だけに対処するのではなく、なぜあなたの身体が天気の変化に敏感になっているのか、その根本原因を見つけることです。
当院では、20年以上の臨床経験と管理栄養士としての知識を活かして、身体と栄養の両面からあなたをサポートいたします。一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。天気に左右されない快適な毎日を、一緒に取り戻していきましょう。

